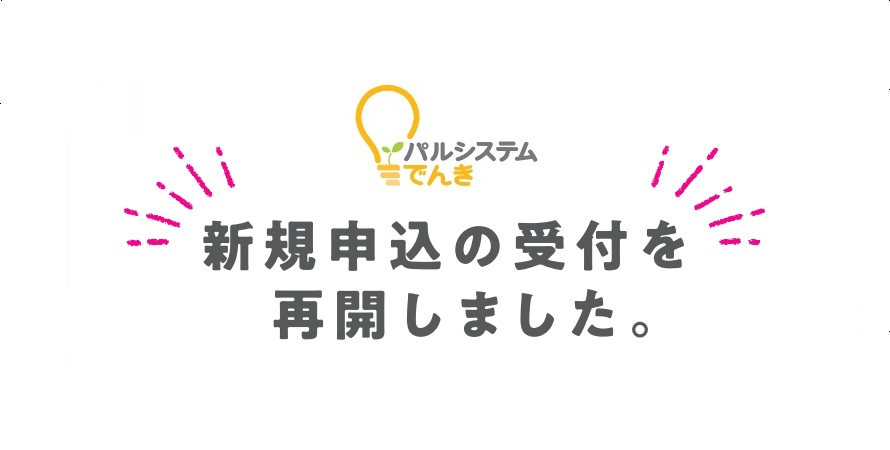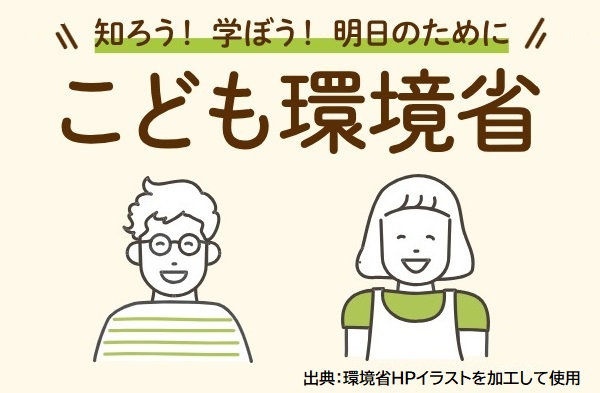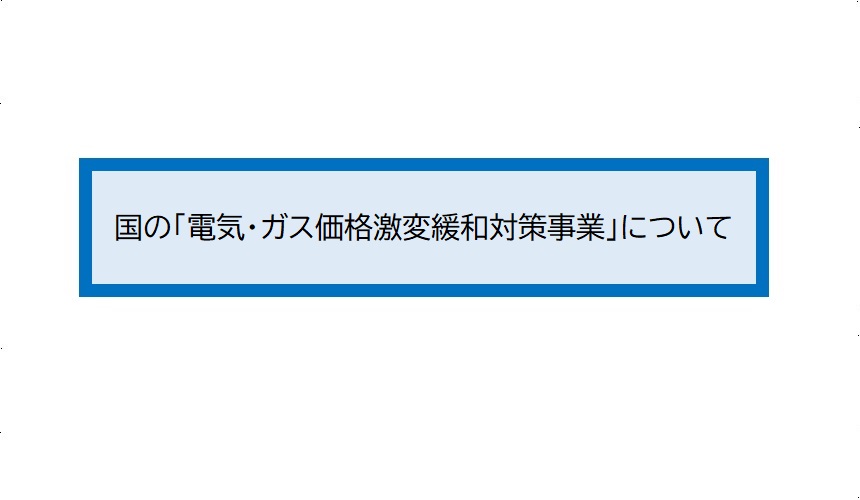Newsお知らせ
Concept 私たちの想い
次世代の子どもたちが
安心して暮らせる社会を
目指して
パルシステム電力は、組合員の
“原発や化石燃料に頼らない 電気を選択したい”
という想いを受け、2016年に電力小売事業を開始しました。
持続可能性と環境保護を重視した再生可能エネルギー主体の子どもたちが安心して暮らせる社会を目指しています。

私たちが電気を選ぶことで
変えられる未来があります
パルシステムは、減らす(省エネルギーの推進)、止める(脱原子力発電)、切り替える(再生可能エネルギーへの転換)のエネルギー政策を制定し、全国の発電産地と連携してFIT電気(再生可能エネルギー)中心の電力供給を続けていきます。

再生可能エネルギー中心で
地域をもっと元気に
「再生可能エネルギーが中心の社会が近い将来実現する」
そのような変化のなかでパルシステムはその役割を担いたいとの想いで、これからも電力事業を続けていきます。